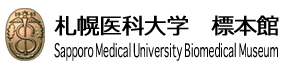このたび,鳥越俊彦教授(医学部病理学第一講座)の退職にともない,2025 年4 月から,標本館⻑を拝命することとなりました.標本館運営委員のみなさまや,標本館専属職員をはじめ,標本館に関わるすべてのみなさまのご理解とご支援のほど,今後とも,よろしくお願いいたします.
標本館は,いうまでもなく,人類の経験や知恵など,これまで人類が経験してきた知識の宝庫です.ここでは,一見単純に思われる「みる」という行為によって,私たちの先達が経験してきた多くの情報を読み取る必要があります.
では,「みる」こととはどういうことでしょうか.少し話がそれるかもしれませんが,お付き合いください.
私は,これまで,病理学を専門領域としてきました.医学部のなかの構成として,病理学は,形式的に,基礎医学分野に属します.しかし,実際は,基礎医学と臨床医学の境界領域に位置し,さまざまな病気について,形態(かたち)や遺伝子レベルで,病気の発生メカニズムを解明する学問です. 病理学では,「みる」ことが重要です.あえて,「見る」とは表現しません.「みる」ことが,すべてのはじまりであり,第一歩と考えています.まずは,「もの」を「みる」ためには,「もの」そのものの概念が必要なことはいうまでもありません.対象となる「もの」の概念を知らないと,「もの」を理解できないことに直結します.結果的に,「もの」自体が「どういうものなのか」と概念がないと,「見えても見えない」うえ「理解もできない」という事態に陥ります.したがって,「見る」ことと「みる」ことは,本質的に異なるのです.この意味において,標本館の第一義的な意味があると考えています.
これまで,標本館では,本学の学生のみならず,中高生や,医療関係,あるいは,医療とは関係のない大学生や専門学校生を対象に,見学を受け入れてきました.彼らにとって,日頃の授業では「みえない」実物の魅力と迫力を感じ取ってもらうことで,充実した医療に関する教育学修の場を提供できていると自負しております.今後も引き続き,このような活動を実践していく所存です.
病気に対するひとの認識を,最近では,新型コロナウィルスのパンデミックの経験などから,病気を「見える化」し,経験と知恵,反省点などを体系的にカタログ化したうえで,アーカイブする重要性が再認識されます.この意味で,標本館は,これまで病気に立ち向かってきた先達の情報を集積する場であり,この情報を後世に伝えなければならない重要な役割をも有しています.これが,まさに標本館の存在価値と考えています.
これからも,関係諸氏のご協力を得ながら,標本館の一層の充実とともに,人類の知恵を幅広く共有できるよう活動していきたいと考えております.関係各位のご理解とご協力をお願い申し上げます.

小山内 誠
病理学講座 病理学第二分野 教授