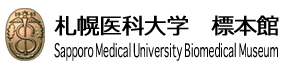▶第39号(2011年 3月1日発行)
縄文人とオホーツク人:発掘された遺伝子
松村 博文
札幌医科大学医学部解剖学第二講座准教授
標本館には、北海道の古代遺跡から発掘された人骨の代表として、高砂貝塚(虻田)の縄文人(約3500年前, 図1)や大岬遺跡(稚内)のオホーツク人(5〜11世紀, 図2)などが展示されている。ほかにも大学の収蔵庫には道内各地の遺跡から発見された古人骨が多数保管されており、その数は369体にもおよぶ。これらは日本列島の人類史を解明するうえで貴重な標本となっていることから、国内外の研究者に活発に利用されており、最近ではDNA分析など分子人類学的研究も盛んに進められている。遺伝子増幅の手段としてPCR法が開発され以来、微量のコラーゲンからDNA分析ができるようになり、数千年前の古い人骨からもDNAの抽出が可能となっている。いわば発掘された古人骨からさらに遺伝子を発掘することができるのである。こうした最先端の人類学研究から、従来の形態学的アプローチでは知ることのできなかったことが次々と明らかにされつつある。本誌では、その一端を紹介する。
|
|
ミトコンドリアDNA
低顔で彫りの深い顔立ちを特徴とする縄文人が、アイヌ民族の祖先であったことは従来の形態学的研究によって明らかにされてきたとおりである。遡って、その縄文人がアジアのどこから由来したのかについては、東南アジア説や北東アジア説などが混交しており、その見解は未だ統一をみない。そこで縄文人の起源を遺伝子レベルで解明するため、山梨大学法医学教室の安達登教授らとの共同研究により(Adachi et al., 2009)、縄文人骨からミトコンドリアDNA(mtDNA)の抽出を試みた。試料は本学に保管されている縄文人・続縄文人の54体分の歯のサンプルである。変異の大きいDループのHVR領域についてAPLP法によりSNP(一塩基多型)の検出をおこなった。その結果、N9b(64.8%), D10(16.7%), G1(11.1%), および M7a(7.4%)という4種のハプログループがそれぞれの頻度でみいだされた。N9bとG1はシベリア先住民にのみにみられる特殊な遺伝子型で、D10も氷河期にシベリアから移住したアメリカ先住民に多いタイプである。一方、M7aは日本列島南部から東シナ海に高頻度で検出されているタイプである。このことは縄文人のmtDNAにはアジアの南北両要素が混在していることを示唆するものであるが、とりわけ北海道の縄文人はシベリアとの関係が深いことを明示している。
縄文人とは対照的に極めて平坦な顔面などを特徴とするオホーツク人は、形態学や考古学からシベリアのアムール河流域から渡来したのではないかと推定されている。そのオホーツク人のmtDNAについても北海道大学理学研究院の増田隆一准教授や佐藤丈寛(現:名城大助教)らとの共同研究により分析がすすめられ、42検体からの抽出に成功している(Sato et al., 2009)。ハプログループYが39.5%と最も多く、次いでG1が23.3%、N9が11.6%の頻度で検出された。ハプログループYはアムール河流域のウリチ族やニブヒ族に特異的に多いタイプであることから、オホーツク人のアムール河流域起源説を裏付ける結果となっている。
耳垢とABO式血液型遺伝子
核DNAは、従来は古人骨試料では断片化が著しく解析が困難であったが、上記の増田・佐藤らとの共同研究により、縄文人やオホーツク人の人骨試料からも、その一部の検出に成功している(Sato et al., 2009)。その一つが耳垢遺伝子である。ヒトの耳垢には乾型と湿型の2タイプがあり、それらの表現型はABCC11遺伝子上のSNPによって決定される。耳垢の表現型の頻度分布は集団により異なるため、古くから集団の特徴を示す人類遺伝学的指標として用いられてきた。北東アジア集団では乾型耳あかの頻度が他地域に比べ圧倒的に高い(80-95%)傾向にある。そのため、乾型の対立遺伝子は北東アジアに起源をもつと考えられている。北海道の縄文人14体とオホーツク人30体のABCC11遺伝子を分析したところ、縄文人の50%が湿型であるのに対し、オホーツク人は84%が乾型であった。耳垢タイプからも、縄文人の南北両要素の混在とオホーツク人の北東アジア由来が支持される。
同じく増田・佐藤らとの共同研究では(Sato et al., 2010)、ABO式血液型の対立遺伝子頻度の分析も行っている。縄文人14検体のSNP解析で検出された対立遺伝子は, A(含A101,A102, A201)が32%、 Bが23%、Oが45%、オホーツク人15検体からはAが8%、 Bが15%、Oが77%というデータが示され、両集団の頻度構成が大きく異なっており興味深い。現状ではサンプル数はまだ十分とはいえないが、先史時代の人骨から血液型が解明できたことは画期的であり、今後の発展が大いに期待できる研究となっている。
文献
Adachi N, Shinoda K, Umetsu K, and Matsumura H. Mitochondrial DNA analysis of Jomon skeletons from the Funadomari site, Hokkaido, and its implication for the origins of Native American. Am J Phys Anthropol 138: 255-265, 2009.
Sato T, Amano T, Ono H, Ishida H, Kodera H, Matsumura H, Yoneda M, and Masuda R. Allele frequencies of the ABCC11 gene for earwax phenotypes among ancient populations of Hokkaido, Japan. J Hum Genet 54: 409-413, 2009.
Sato T, Amano T, Ono H, Ishida H, Kodera H, Matsumura H, Yoneda M, and Masuda R. Mitochondrial DNA haplogrouping of the Okhotsk people based on analysis of ancient DNA: an intermediate of gene flow from the continental Sakhalin people to the Ainu. Anthropol Sci 117: 171-180, 2009.
Sato T, Amano T, Ono H, Ishida H, Kodera H, Matsumura H, Yoneda M, Dodo Y, and Masuda R. Polymorphisms and allele frequencies of the ABO blood group gene among the Jomon, Epi-Jomon, and Okhotsk people in Hokkaido, northern Japan, revealed by ancient DNA analysis. J Hum Genet 55, 691-696, 2010.