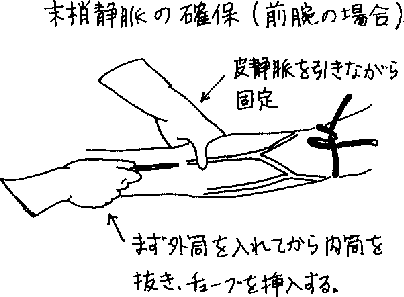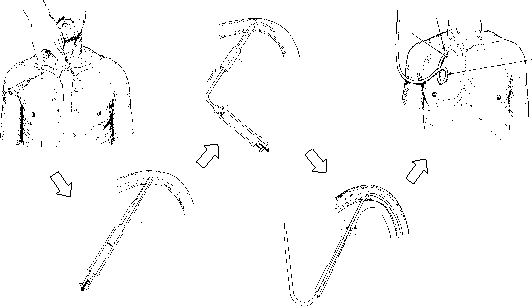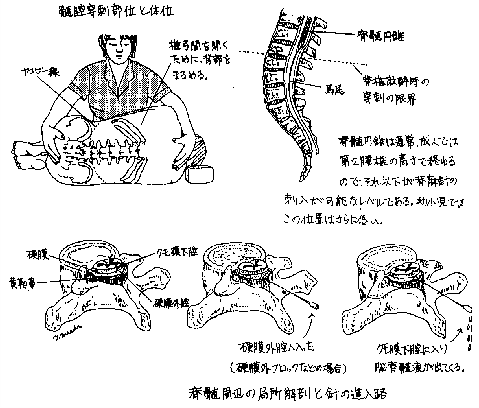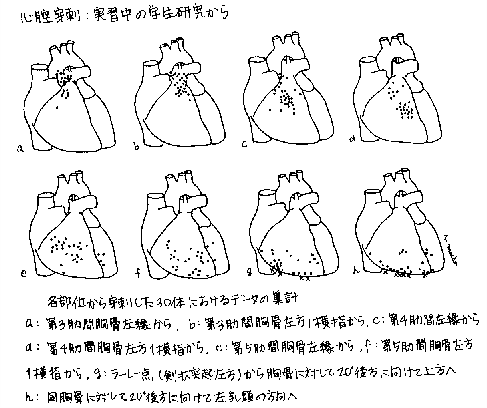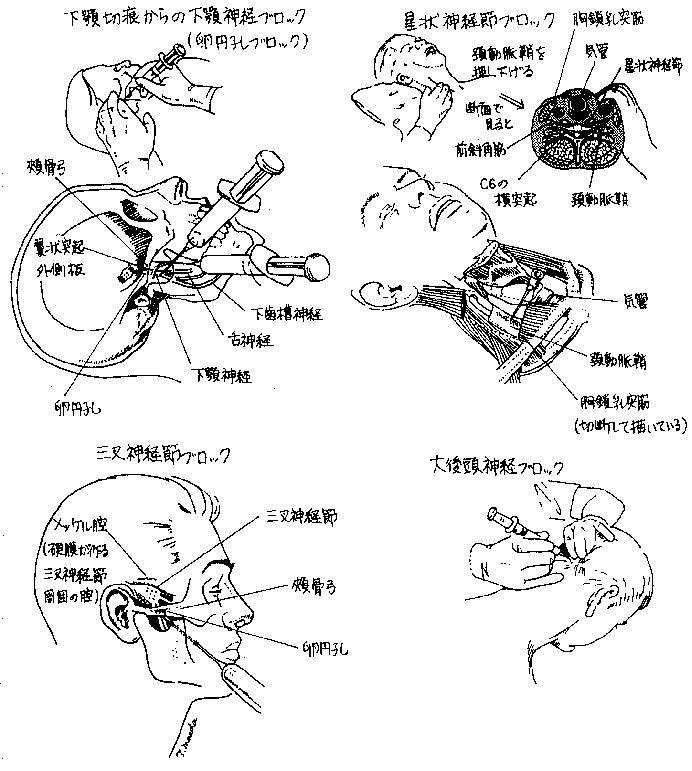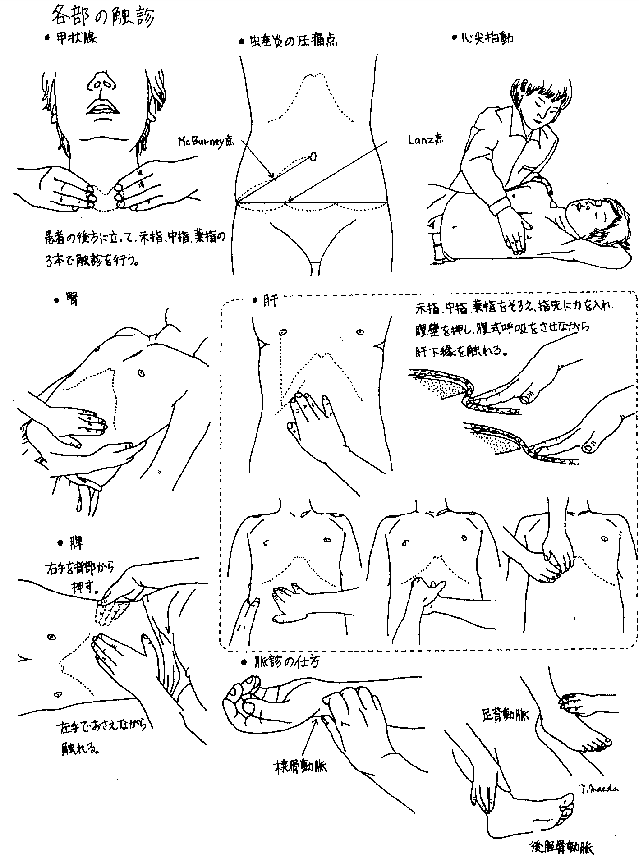| Intermuscular septum(septa) | 筋間中隔 | |||
| Medial brachial - | 内側上腕筋間中隔 | 46 | ||
| Medial femoral - | 内側大腿筋間中隔 | 614 | ||
| Posterior femoral - | 後大腿筋間中隔 | 614 | ||
| Sciatic nerve | 坐骨神経 | 513 | Nervus ischiadicus |
特に下記の部位で必ず実施する:
以下の臨床基本手技を模してライヘに行ってみる。解剖の進行状況によってそのつど指示する。
背部の剖出中、遅くとも深背筋の剖出(p.![]() ) までに行なう。
) までに行なう。
ヤコビー線 は腸骨稜の最高点を結ぶ線で、4-5腰椎間付近を通る。
手技説明はビデオで行なう。刺した針は当日内に返却する。
骨に当たらずスッと針がはいる感触を知る。
ルンバールは麻酔目的の他に診断でも用いる基本手技である。
麻酔科医の研究のため白いゴム液を3-4ml注入してある。
基本手技中の基本手技。
長期絶食の場合、生存に必要な栄養(高カロリー輸液)
を皮静脈からは投与できない。静脈炎 をおこし激痛をともなうからである。そのため、鎖骨下静脈から上大静脈へカテーテルを通して高カロリー輸液 を流す。
意識のない患者の気道を確保し、レスピレーター (人工呼吸器)につなぐため、気管内にチューブを挿管する。喉頭鏡を用いて確実に喉頭展開 しないと、食道挿管という失態をおこす。
トラカール針という太い管を用いて肋間から胸膜腔にチューブを通す。胸膜炎 は高齢者や末期にしばしば見られ、抗生剤投与だけではなかなか改善しない。体位交換によって胸水を穿刺部位に集める必要がある。
心停止時にボスミンを直接心腔内に注入する手技は、現在救急現場ではほとんど行われない。しかし、全国的に市中病院では死亡確認のためしばしば行われている。実際には、刺しやすい右室に注入していることが多いと思う。