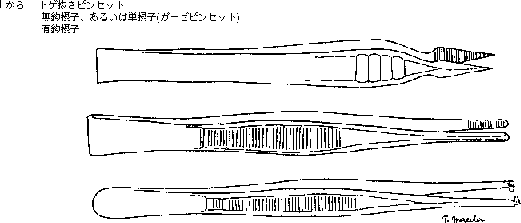初版の序(渡邊佐武郎名誉教授、三橋公平名誉教授)
解剖実習の心得
1.人体を解剖するということは、医学を学ぶ者のみに許された行為である。遺体は生前か
ら”自分の体を正しく解剖することによって、諸君が立派な医師になって欲しい”という希望を抱いていた篤志家のものである。したがって、遺体には常に敬虔の念を持って接し、丁重に取り扱わねばならない。
2.実習に当たっては、予め充分に予習をしてくる必要がある。準備なしに実習を行うこと
は、解剖体を冒涜することである。
3.一つの遺体を数人で解剖するのであるから、互いに協力し、自分の分担部に責任を持
つことは言うまでもないが、同時に全体の観察も怠ってはならない。
4.実習台の上は常に清潔に保ち、同時に実習室の保清、整頓を心掛ける。間違っても、
実習室に土足で入るようなことがあってはならない。
5.遺体は乾燥しやすいから、頻繁に防腐液を散布する必要がある。
6.実習の進行は、本指針の記載に沿って行う。筋、血管などの切断及び除去、内臓の摘
出などは、必ず指針の指示に従い、順序良く行うこと。
7.遺体から除去した脂肪、結合組織、器官の一部などは、備付けの容器の中に入れること。
8.破格を発見したときは、直ちに教員に報告し、指示を仰ぐこと。
9.実習室内での喫煙、飲食などは固く禁ずる。
10.実習室の白衣および上履きは、解剖実習室専用とし、室外では使用しないこと。
11.遺体は充分に固定、防腐されているので、手の負傷など特別な理由のない限り、手術
用手袋の使用は認めない。(現在ではどこの大学でも許可されている:村上)
12.許可なくして学外の者を実習室に入れることを禁ずる。
13.納棺は教員と技術員の指示にしたがって行い、間違ってもメスやピンセットなどの金
属品が混入することがないように注意する。
本書の使用方法
本書は解剖の手順を解説したものです。第2章以降は、基本的にはどこからでも始められるように作られていますが、別途配布する予定表に概ね準拠して下さい。臨床の医師たちによって実習中に行われる研究の予定も、後日配布します。
(Fig.○○)は、Carmine D. Clemente, ANATOMY, the regional atlas of the human body, 4th ed., 1997 の Fig. 番号を示しています。
小節(例えば、1.2.3)の見出しにある(Fig.○○)は、その小節に関するFig.の中でもキーとなるFig.の番号です。本文中にある(Fig.○○)は、解剖を進める際に参考にすべきFig.です。
本文中にはまた太字で書かれているノミナがあります。これらはノミナの整理としてまとめてあります。ノミナ確認、クレメンテ参照の際にご利用下さい。
ノミナ整理の各ノミナにはFig.番号が添付されています。これは本文に沿って解剖を進め各ノミナの組織を確認する際に参照すべきFig.で、各ノミナに対して最も適切なFig.が添付されています。○○ ![]() はクレメンテのFig.に記載のないものを、○○
はクレメンテのFig.に記載のないものを、○○ ![]() はクレメンテ各Fig.の解説文中に記載のあるものをそれぞれ示しています。*の付いたノミナは、和訳を求めることはありますがスペルは書けなくてもいいものです。
はクレメンテ各Fig.の解説文中に記載のあるものをそれぞれ示しています。*の付いたノミナは、和訳を求めることはありますがスペルは書けなくてもいいものです。
なお、さらに他のFig.を参照されたい場合はクレメンテの索引をご利用下さい。
■付図(ピンセットの名称)